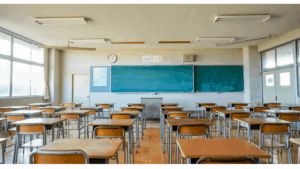今日は、病気と向き合いながらも前向きに生きる姿勢で多くの人に勇気を与えている瀬戸あゆみさんについてお話ししたいと思います。彼女は脊髄小脳変性症という難病を抱えながらも、自分らしい人生を歩み続けています。その生き方には、たくさんの学びと希望が詰まっています。
脊髄小脳変性症の概要

瀬戸あゆみさん(31歳・当時)は、2025年2月3日に自身のInstagramで「脊髄小脳変性症」を患っていることを公表しました。症状としては、歩行時のふらつき、手の不器用さ、ろれつがうまく回らないなど、あらゆる運動機能に障害が出ているとのことです。
この病気には根本的な治療法がなく、リハビリによって進行を遅らせることしかできません。一般的には数年後には歩行困難に至り、車椅子や寝たきりになることも多く、長寿も難しいとされています。
公表に至った想い
瀬戸さんが難病を公表した主な理由は2つありました。
言わずにいる限界を感じたため
病気の進行によって「外見的な変化」が目立ち、人の視線が気になるようになったこと。「大丈夫ですか?」の言葉が増え、外出すら億劫になってしまう…そのような悪循環を断ち切るには、公表しかないと判断したそうです。
同じような病気の方々との情報共有
同じ病に苦しむ人や、これから子どもを持ちたいと考える人の少しでも支えになれればという思いから、「こんな私でも、誰かの役に立てたら」と発信を続ける意志も語っていました。
現在の状況と発信について
2025年4月には入院されていたことも明かし、体調との日々の向き合いを続けておられます。また、32歳の誕生日を迎えた際には「また日々がんばります!」と自身を鼓舞する投稿もされており、強い前向きさを感じさせます。
あなたに伝えたいメッセージ
瀬戸さんの姿勢から学べることはたくさんあります。
- 正直に生きる勇気:病気という「見えにくい」苦しみにも、目を背けずに語る強さ。
- つながりの大切さ:同じ境遇の人と情報を分かち合うことで、孤独が希望に変わること。
- 前向きな発信:「まだ伝えたいことがある」と、自らの声で誰かの力になろうとする姿勢。
瀬戸あゆみさんの“克服”という言葉は、病気の完治を意味するものではないかもしれませんが、「生きる姿勢」で病と向き合っていること、そして病気を通じて誰かに勇気や共感を届けようとしているその姿こそが、まさに“克服”の一環なのだと感じます。
脊髄小脳変性症とは?
脊髄小脳変性症(英語では Spinocerebellar Degeneration (SCD) または Spinocerebellar Ataxia (SCA) とも呼ばれます)は、小脳や脳幹、脊髄などの神経細胞が徐々に「変性」・消失していくことで、主に運動失調(協調運動障害やバランスの喪失など)を引き起こす一群の神経変性疾患です。以下に要点を整理しました。
概要と定義
総称的な疾患群であり、「脊髄小脳変性症」と呼ばれる一つの病気ではありません。小脳に限らず、脳幹や脊髄にも影響を及ぼします。
症状の原因には多くが「原因不明の変性」であり、以前は腫瘍・血管障害・炎症・栄養障害などが除外された後に「変性症」と総称されるケースが多かったです。
主な症状
運動失調:筋力は十分あるのに、滑らかに動かせない(例:ふらついて歩く、箸やペンがうまく使えない、ろれつが回らない)
手指の震え、バランス障害、構音障害なども典型的です。
その他、パーキンソン症候群(こわばり・動作緩慢)、末梢神経障害(しびれ・感覚鈍麻)、若年発症では知的障害やてんかんの併発もあり得ます。
分類:遺伝性 vs. 孤発性
遺伝性タイプ:家族内で同様の症状があるケース。常染色体優性・劣性、X染色体や母性(ミトコンドリア)形式など多様な遺伝形式があります。
孤発性(非遺伝性):家族歴がないタイプで、患者全体の約7割を占めます。主に多系統萎縮症(MSA)や皮質性小脳萎縮症(CCA)などが含まれます。
日本における状況
指定難病(18番)として認定されており、平成24年度には医療受給者証保有者数が約25,447人と報告されています
全国推計では、約3万人の患者がいるとされています。
そのうち約1/3が遺伝性と推定され、主にSCA3(マシャド・ジョセフ病)、SCA6、DRPLAなどが頻度の高い病型です。
スピンコセレベルアタキシア(SCA)としての視点
国際的には「Spinocerebellar Ataxia (SCA)」という用語で遺伝性の分類が整理されています。
現在、40以上の遺伝型(例:SCA1, SCA2, …)が特定されており、遺伝子変異の多くは**CAGリピート(ポリグルタミン関連)**や他の繰り返し配列拡張に関連しています。
治療と予後
日本のある形式(多系統萎縮症など)は進行が早く、数年で介護状態に至ることもあります
根本治療は未確立ですが、対症療法(リハビリ、Speech therapy、バランス訓練など)により症状の緩和や進行の遅延を目指します。
特定された遺伝子を対象とした研究(動物モデル、遺伝子治療など)が進行中です。
瀬戸あゆみの公表した難病とは?
瀬戸あゆみさんが公表された難病は、ご自身がInstagram上で明かされた通り、「脊髄小脳変性症」です。
2025年2月3日、モデルかつブランドプロデューサーとして活動する瀬戸あゆみさん(当時31歳)は、インスタグラムで難病である「脊髄小脳変性症」を患っていると公表しました。
実際に子どもを産んで、はじめて母の気持ちがわかった。ってことが、とてもある。
ああ、あのとき、母はだからあんな風にしてくれたのか、と。母はわたしと同じ病気だった。
母は若くして、21歳で、わたしを産んだ。
病院の記録によると病気を発症したのは30歳で、それまでは(っていうか記憶ではそれ以降も)普通のお母さんとして、わたしを自転車の後ろに乗せて、スーパーに買い物に行き、晩ごはんを作っていた。
夏休みにはわたしを退屈させないように、電車で都会に出たり、時には車で田舎に行ったりもした。そして、わたしは31歳で母になった。
母との差は10つある。
そしてこの病気は進行性で、わたしも母と同じく30歳ごろに発症、ということになっている(特にはっきりとこの時に症状が出た、ということが断言しづらく、段々とゆるやかに症状が出るのが特性の病気なので、こういう書き方になります)。ここまで書いて勘がいい人はお察しだろうが、問題は、わたしはいつまで母を続けていけるだろうか、ということだ。
この病気について彼女は「小脳がどんどん破壊・消失していく」神経疾患であり、主に歩行時のふらつき、手の不器用さ、ろれつがまわらないといった運動失調が「今はすべての症状が、大小あれどわたしに出てきている」と述べています。
お母様も同じ病気だったんですね。子育てしながら本当に大変な思いをされたんですね。
ご本人の言葉と報道によると、治療法は確立されておらず、リハビリによって進行を遅らせることが現状における主な対処となるとのことです。
SNSでの告白とリハビリ生活
2025年2月3日、モデル・プロデューサーとして活動する瀬戸あゆみさん(当時31歳)は、自身のInstagramで、指定難病「脊髄小脳変性症」を患っていることを公表しました。
投稿では、以下のように病状を率直に説明されています。
「病名は、脊髄小脳変性症というものです。運動神経を司る小脳がどんどん破壊・消失してゆき、運動失調を主な症状とする神経疾患の病気です。主な症状としては、歩行時にふらつく、手がうまく使えない、口や舌がもつれて話しづらいなどです。今はもうすべての症状が、大小あれどわたしに出てきている感じです」
さらに、治療の現状についてもこう記しています:
「現在の医学では明確な治療法は確立されておらず、リハビリで進行を遅らせるしかありません。リハビリ次第ではあるけれど、数年後、歩けなくなり、車椅子に乗るようになり、寝たきりになる可能性もあり、長生きは難しいという一般的な予後です」
公表に込めた2つの想い
瀬戸さんがSNSでの公表に踏み切った理由として、以下の2点を挙げています.
「言わずにいる限界」への覚悟
歩き方が目に見えておかしくなり、「大丈夫ですか?」と声をかけられることで、外出することへの恐れや悪循環に陥っていたこと。だからこそ公に知らせる決断をしたのだと語っています。
同じ境遇の人への発信とつながり
「同じような病気の人と情報交換できたら」「子どもを持ちたい人に何か役立つことが伝えられるかもしれない」「こんなわたしでも誰かの役に立てたら嬉しい」と、発信を続ける動機も明かしています。
投稿後、多くの方から励ましのコメントや温かい反響が寄せられ、「公表してよかった」との思いも述べられています。
リハビリ中心の生活と闘病の日々
瀬戸さんは「明確な治療法はない」としながらも、リハビリによる進行の遅延に希望を持って日々取り組んでいると語っています。加えて、出産後は動かない時間が増え、体への変化をより感じるようになったと述べており、日常生活の中で病気と向き合いながらのリハビリ生活が続いていることがうかがえます。
入院と“日常への復帰”
2025年4月10日付のInstagramストーリーでは、高熱のため入院していたことを報告。その後、無事に退院し、義実家への旅行や息子さんの入園式へ参加など、ハードな日々を乗り切ったと振り返っています。
退院後にはSNS活動も再開し、支えてくれる家族や友人への感謝を綴りながら「SNS復帰します」とあなたへの発信も再開する強い意志を見せています。
発信の力と日々の闘い
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 公表の場 | SNS(Instagram) |
| 病名・症状 | 脊髄小脳変性症:小脳の退行による運動失調、ふらつき、構音障害など |
| 治療状況 | 根治なし。リハビリ中心で進行を遅らせる |
| 公表の目的 | 「言わない限界」「同じ境遇の方へのつながり、情報共有」 |
| 入院以降 | 高熱で入院 → 退院後も子育てなど日常生活を送る力強さ |
| 発信姿勢 | 前向きさ、感謝、自らの経験を通じた誰かへの希望や支えの提供 |
瀬戸あゆみさんのSNSでの告白には、率直さと他者への思いやりが感じられます。その後の日々のリハビリや入院生活の報告も、同じ病と闘う方やその家族にとって大きな勇気と希望になることでしょう。
子どもとの関わりとリハビリ
こちらは瀬戸あゆみさんが息子さんと寄り添う様子を写したお写真です。お子さんとの関わりを深めている、そのあたたかな日常が伝わってきますね。
瀬戸あゆみさんの「子どもとの関わり」と「リハビリ生活」
子どもとの関係性:母としての日々
瀬戸さんは2024年3月に待望の第1子となる男の子を出産し、その喜びと愛情あふれる日々をSNSで時折共有しています。病気を公表した際には、「淡々と語る」としながらも、その投稿からは息子さんへの深い思いや愛情が伝わり、温かな家庭の絆が感じられます。さらに、公表を決断した理由の一つとして、ファンや周囲から寄せられた励ましのコメントが大きな支えとなったことを綴っており、その声援が息子さんとの生活をより豊かに彩る力となっている様子がうかがえます。
病気を公表した際には、「淡々と語る」としつつも、その背景には息子さんへの思いや愛も感じられる投稿が多く、温かな家庭の中で支えられている様子がうかがえます。
また、「公表してよかった」と感じられた理由の一つとして、ファンや周囲からのコメントに励まされたと綴られており、その声援はお子さんとの生活を支える大きな力にもなっているようです。
リハビリ生活のリアル:ブログより
瀬戸さん自身が綴るブログでは、具体的なリハビリの様子が生々しく描かれています。2025年4月14日の投稿では以下のような内容が紹介されています。
- ベッドで体全体のマッサージ
- 歩行器を使った立ち上がりと足踏み
- トレッドミルでの歩行練習(約3分)
- 歩行器を使ってリハビリ室を移動し、トイレまで歩く訓練
理学療法士(PT)の指導のもと、日々の小さな積み重ねが彼女の日常を支えているのが伝わります。
リハビリの専門的背景:効果と手法
医学・リハビリの視点からみると、脊髄小脳変性症におけるリハビリには以下のような意義と方法があるとされています:
| リハビリの目的 | 内容 |
|---|---|
| 転倒予防・安全な歩行 | バランス・歩行訓練、体幹強化、歩行器や杖の活用など |
| 日常生活の維持(ADL向上) | 作業療法でボタン掛けや箸の選び方など工夫 |
| 長期的な効果と機能改善 | 短期集中リハで運動失調が改善し、半年〜1年持続する例も |
| 最新技術・機器の導入 | ロボットスーツ(HAL®)や歩行支援ロボット(curara®)による支援 |
子どもとリハビリの両立に学ぶこと
瀬戸さんの姿から見えてくるのは、母親としての愛情の深さと、リハビリの地道な継続の重要性です。
- 小さなステップの積み重ねが、生活の中に安定と希望をもたらす。
- 理学療法士との信頼関係や指導が、リハビリへの意欲を支えている。
- 子どもの存在が、発信や闘病の原動力にもなっている。
- 支えてくれる周囲への感謝は、発信や日常を前向きに保つエネルギー。
難病に対する世間の理解
「難病に対する世間の理解」について、最新の調査結果や社会の取り組みを踏まえて以下に整理しました。
社会全体の理解不足と偏見
約72.3%の一般市民が「難病についてほとんど知識がない」と回答し、多くが理解不足の状態にあります。
結果として、患者さんの約43.8%が「社会生活で困難を経験している」と答えており、とりわけ外見から判断しにくい症状ほど理解が得られづらい状況です(最大58.7%)。
職場や地域での見えない負担
難病の症状には疲労や痛みなど「外見では分からないもの」が多く、73.2%の患者が「周囲に理解されづらい」と感じています。
就労場面では約58.5%が「職場での理解不足による困難」を経験し、そのうち33.7%は病気を開示していないと回答しています。
精神的負担と社会的孤立
約62.5%の患者が「将来への不安」を抱え、43.8%が「周囲の理解不足」によるストレスを感じているという調査結果もあります。
特に20〜30代の若年発症者では、67.3%にものぼる人が「同年代との交流減少」を感じており、孤立のリスクが高まっています。
情報アクセスと制度の周知不足
約35.7%の患者が「利用可能な制度やサービスに関する情報が手に入りにくい」と感じており、特に高齢者や学歴が低い層ではその割合が52.3%と高い傾向にあります。
制度へのアクセスと情報理解に大きな格差があり、支援を必要としているのに届かない「情報格差」の問題が浮き彫りになっています。
制度・支援整備への要望
難病患者のうち43.5%が「周囲の病気への理解が不十分」と感じており、61.2%が「最適な治療法・治療薬がない」、45.3%が「将来の見通しに不安がある」と回答しています。
医療や社会資源を活かすための情報提供、支援制度の改善、治療の選択肢拡大が強く求められています。
社会的取り組みと啓発の必要性
「理解」だけでなく、合理的配慮に基づく具体的制度化が不可欠であるとの指摘があります。また、教育現場やSNSなどを通じた次世代への啓発活動も期待されています。
患者自身の発信やコミュニティの力
自らの経験をブログやSNSで発信することで、共感や孤立の軽減につながるというポジティブな効果が報告されています。自信の声が社会理解への第一歩になるとされています。
さらに、RareConnectのように、国内外の難病患者同士がつながりをもつオンラインコミュニティが存在し、情報共有や支え合いの場として機能しています。
現状と望まれる姿
| 項目 | 現状 | 必要な対策 |
|---|---|---|
| 意識・理解 | 多くが病気を知らず、偏見・誤解がある | 啓発・教育、合理的配慮の導入 |
| 孤立とストレス | 精神的負担が高く、孤立や交流不足に苦しむ | 地域コミュニティ・支援体制の充実 |
| 情報・制度のアクセス | 情報格差・制度の理解不足が深刻 | 情報発信の強化、制度の簡略化 |
| 患者の主体性 | 発信やコミュニティが理解を促進 | 患者参加型の施策拡大、発信支援 |
| 制度への反映 | 声が政策や医療に届きにくい現実 | 当事者の声の制度反映、社会構造の改革 |
社会全体の理解を深めていくためには、教育、メディア、行政、企業、医療現場、そして患者・家族の声すべてが結びつくことが重要です。
瀬戸あゆみから学ぶ生き方
瀬戸あゆみさんから学べる生き方は、多くの人にとって大切なヒントになりそうですね。以下、彼女の言動や姿勢を通じて見えてくる“生き方の哲学”を整理しました
1. 「本当は強くない」と認める勇気
瀬戸さんは、難病を公表する際に「本当は全然強くない」と自分の弱さを率直に告白しました。その葛藤や迷いを正直に語る姿からは、弱さを包み隠さず受け入れる強さが伝わってきます。
2. 公表するまでの葛藤と、それを乗り越える一歩
発信直前までは「やめたい」「何かが180度変わってしまう気がして」と葛藤があったという瀬戸さん。それでも一歩踏み出すことで、自己表現と新たな可能性が開けることを示しています。
3. 病気のリアルを冷静に伝える姿勢
彼女は病名や症状を淡々と説明し、感情に流されない“情報の伝え方”にこだわりました。これは冷静さと思いやりの両立を象徴する姿勢です。
4. 「もう言わないことに限界を感じた」正直さ
他人の視線に敏感になり、外出にも消極的になる…その「限界」を、自分自身に正直に認めた瀬戸さんは、自己理解を深めることで行動が変わる実例を示しています。
5. 仲間や支援者への感謝と共に歩む姿
フォロワー増加の驚きに加え、「応援してくださる方が多くて、本当にありがたいです」と感謝の言葉を示す瀬戸さん。周囲への感謝とつながりを力に変える強さが感じられます。
6. お仕事=リハビリ、自分らしさの源
自身のブランド運営や仕事を、自分の“ID(アイデンティティ)”と語り、「働くことが病気を忘れられる唯一の時間」と表現。活動の継続が生きる力になることを明言しています。
7. 患者同士のつながりへの意欲
同じ病気を抱える人たちとの情報交換や交流に積極的な姿勢を見せ、「どうやって情報を交換していけばいいのか…ちょっと考え中」と前向きです。当事者同士の支え合いを重んじる姿勢が光ります。
8. 家族や支える人への信頼と依存
闘病・育児の両立の中で、夫、保育園、ヘルパー、友人、仕事仲間、家族など、さまざまなサポートに支えられていると明かした瀬戸さん。助けを求め、頼ることの素直さもまた大きな強さです。
生き方としてのまとめ
| キーワード | 学び・意義 |
|---|---|
| 弱さの受容 | 「本当は強くない」と認めることで、自分を許し、前に進む |
| 公表の勇気 | 恐れの先に、新たな可能性と支え合いが広がる |
| 冷静な語り | 病気のリアルを淡々と伝えることで、理解と共感を生む |
| 正直な限界 | 自分の限界を認めることで、適切な行動へ踏み出せる |
| 感謝の姿勢 | 支えてくれる人たちへの尊敬が、人とのつながりを強くする |
| 仕事=存在の表現 | 活動は自身の生きる力/リハビリそのものという捉え方 |
| コミュニティの力 | 共感や交流が、希望と情報の源になる |
| サポートに頼る潔さ | 周囲を巻き込むからこそ、持続できる生き方がある |
瀬戸さんの言葉や行動は、自己肯定・支え合い・発信の大切さを教えてくれます。生きづらさを抱えた時、まず自分の弱さを認め、支えを求めること。仕事や発信を通じて自分を取り戻し、誰かとつながること。彼女の姿には、そのすべてが詰まっています。
最後に
瀬戸あゆみさんの生き方から学べることはたくさんあります。病気や困難に直面している方だけでなく、どんな人でも彼女の姿勢から勇気と希望を得られるでしょう。人生は時に厳しいものですが、その中でも自分らしく生きる力を持つことが大切です。
今日の記事が少しでも誰かの心に響けば嬉しいです。瀬戸あゆみさんのように、前向きな一歩を踏み出す勇気を持ち続けたいですね!